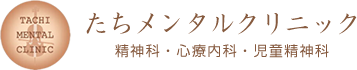臨床コラム 「彼は6時5分過ぎに家を出たのだが,それから1時間後,豚のように滅多切りにされる」
ガルシア·マルケスによる『予告された殺人の記録』は,小さな町で行なわれた盛大な結婚披露宴の翌朝,サンティアゴ・ナサールが5時半に起きて7時すぎに死ぬまでを描く。作家は,自身の住んでいたコロンビア内陸の町スクレで起きた殺人をもとに執筆し,事件の30年後にこの小説を出版した。
披露宴のあと新郎は,新婦が生娘でなかったことを知り,新婦の実家へ返した。親きょうだいが娘を問い詰めると,サンティアゴ・ナサールの名が出てきた。双子の兄たちは,一族の名誉のために彼を殺すと宣言した。 宴の興奮が冷めぬ街のなかに,野火のごとく噂は広がり,誰もが知るところとなる。そして予告は,実現した。
物語は,事件の起きた朝の経過,宴の乱痴気ぶり,当事者たちの来歴,事件後のこと,そして30年ほどの時を経た地点にいる「わたし」を織り込んで進みゆく。いくつもある時間の流れが,ひとつのうねりとなり,ただ一点へと向かう。つまり,サンティアゴ・ナサールは死ぬ。必然ゆえの偶然の重なりによる殺人。そして双子は,のちに無罪となる。
それぞれの果たした役割を,「わたし」は追い求める。この町にいた人すべてが,当事者だからである。執拗なまでの調査は,30年近くに及ぶ。そのなかで,奇妙な点が浮かび上がる。数十人に上る登場人物のうち,被害者が被害者であることの,そして「わたし」が「わたし」であることの必然性が,奇妙なまでに薄い。
なぜ彼は,死なねばならなかったのか。なぜ「わたし」は,追い求めるのか。
探究の足取りは,『オイディプス王』のそれに似る。オイディプス,イオカステ,ライウスはみな,「子が父を殺し,母と交わる」という神託の実現を避けようとした。しかし彼らのふるまいはいずれも,実現への歩みとなる。彼らは,そのために存在するからである。テーバイの市民たちは,その証人となる。オイディプスは父を殺し,母と交わる。真実を求めてそれを知り,自らの目を抉り,テーバイを出た。神託による物語の実現を妨げられる者は,誰もいない。ライウスがかつてペロプスの食客だったころ,その息子を掠めたとき,まだ生を受けぬオイディプスの宿命は定まった。
死ぬのが,サンティアゴ・ナサールである必然性はない。語るのが,「わたし」である必然性はない。ただ2人の宿命がそうであったにすぎない。宿命という物語は,担い手が必要であるために,人を選び取る。人がそれを選ぶことは,できない。しかしその担い手となるや,物語が人を動かす。必然は物語にある。人にあるのではない。
双子に滅多切りにされたあと,彼が死ぬまでの描写は,優雅で美しい。彼は垂れ下がった腸を抱え,自宅の門から裏口へと,歩いて家に入る。
「サンティアゴ!」と彼女は彼に向かって叫んだ。「どうしたの」
「おれは殺されたんだよ,ウェネ」彼はそう答えた。
彼は最後の段につまづいて転んだ,が,すぐに起き上がった。「まだ,腸に泥がついたのを気にして,手でゆすって落したほどだったよ」と叔母のウェネはわたしに言った。それから彼は,6時から開いている裏口から家に入り,台所で突っ伏したのだった。
こうしてある物語が,幕を閉じる。
私たちは,サンティアゴ・ナサールのように死ぬことになる。「わたし」のように追い求めることになる。私たちは,それぞれが物語の担い手である。だがどのような物語かを知らない。セラピーは,それを明るみに上らせる営みのひとつである。ある2人が出会うとき,もっとも少ない数の当事者たちによる新たな物語の幕が開くのである。
(文責:増尾徳行)