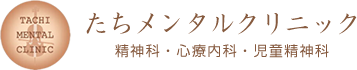臨床コラム 僕と筑紫とヒラギノと
たぶんこのエントリではフォントの違いは反映されないと思うけれど,いま僕はこの文章を「筑紫Aオールド明朝」で書いている。これまでは「ヒラギノ角ゴproW1」(以下ヒラギノ)で書いていることが多かったのだけれど,さいきん試みにいろんなフォントに手を出している。その結果「筑紫Aオールド明朝」(以下筑紫)が気に入ったのである。これを使って文章をあれこれ書いていて,ふいにある感覚に見舞われた。それは,普段遣いのヒラギノがそのまま自分の内的な思考でのフォントになっていて,ひとたび異なるフォントで文章を書いてみたとたん,自分で書いたものに感じられない,という感覚だった。
いったいなんの話をしているのか,わけがわからないと思われる方がいると思う。それは僕もそうである。自分がなにを言っているのか,自分でもまだよくわからないし,ここからいったいなにをどう書いていくつもりなのかもわからない。フォントとか考えたこともないという人もたくさんいると思うし,俗にフォント警察と呼ばれるような小うるさい人もいるかもしれない。いつも食べていた米がコシヒカリからササニシキになったような,コーラからペプシになったような,iPhone13がiPhone19になったような,そんな些細な違和感である……のかどうかもわからないけれど,とにかく,異なるフォントを使うことで,自分の思考が異質なものに感じられるという奇妙な体験がもたらされた。
しかし,それでは,自分「の」思考とは,いったいなんなのだろう? あえて「の」に括弧をつけたのは,格好をつけたのではなく,格助詞としての意味を強調するためである。つまり,自分自身に所有されて,帰属されて,限定されているところであるはずの思考なる現象が,たかだか視覚的記号の形式であるフォントの違いで影響を受けることが本当にあるのかどうか,あるのだとすればそれはいったいなぜか,そして自分の思考とはなんなのか,という,たいへん深遠で広範なテーマを考えているのである。
ひとつずつ考えてみよう。
まず,フォントの違いが思考の所有性に対して異質さを与えた,という現象についてである。フォントとは内容(コンテンツ)の違いではなく,形式(フォーム)の違いである。違うフォントで書かれていても,言葉自体の意味は同じである。このことを当然,僕たちはわかっている。手書きされた「水」であれタイプされた「水」であれそれは同じ意味だし,柄やサイズが違ってもTシャツはTシャツである。フォントにはフォントごとの形式のコンセプトが,哲学がある。会話の中で,何を言っているかに注目するか,どんなふうにどんな言葉で言っているかに注目するか,の違いが,そのまま内容と形式の違いである。
例えばここまで書いてきた内容を,会話にしてみたとする。
「このあいだ,日記のフォントをヒラギノから筑紫に変えたら,自分の文章が自分の文章じゃない感じがしたんですよね」
「なにを言っているのか,意味がわからないんだけど」
「なんでわからないんですか。いつもの米がコシヒカリからササニシキになったときみたいなものです」
「そんなの気付くわけないし,なおさら意味がわからない」
「とにかく,自分の文章が,自分の考えが自分のものじゃなくなったっていうか,異質な感じがしたんです。これは深遠なテーマですよ。記号論的言語学に一石を投じる重大な問題提起です」
「へえ,そうなんだ。ところで,ほしいコラボTシャツがあるんだけど,お金貸してくんない?」
といった感じである。これは,ここまで叙情的形式で書いてきたものを,会話形式に置き換えたものである。多少ウイットなやりとりが含まれてしまったけれど,内容自体はそれほど変わらない。違うのは,形式である。しかし形式が違うと,それを発する側にも受け取る側にも,異なる経験が生じてくる。難しい文庫本を読むよりも,漫画化,映像化されるほうが好まれる。古文のままよりも,現代語訳してほしいと思ってしまう。書いてある内容は同じでも,形式が異なることによって,僕たちの体験は変わってくる。
このようなことから,フォントの違いという形式の違いが体験の違いという作用を生じさせる可能性がありうる,ということが説明できたと思う。
それでは次に,フォントという形式の違いが,自分の文章が自分で書いたものとは思えないという異質さとして経験されたのは,どういうわけなのだろう。ふだんのフォントとは違うからだ,というのは状況的説明であって,理由にはならない。なぜ形式が違ったときの経験が,ほかならない異質さでなければならなかったのだろう?
有力な可能性のひとつに,「慣れ」はあるかもしれない。ヒラギノに慣れていて筑紫には不慣れなので,その不慣れさを異質さとして感じた,ということである。しかし,そもそも筑紫を選んだのは僕なので,ポジティブな印象を持って事態ははじまっているはずであるのだから,そんなに違和感を持たなくてもいいようにも思える。不慣れなものすべてが,異質であるということでもない。これについての仮説は,実はすでに書き出しで触れている。つまり,僕の思考内容を書きだす標準的な形式がヒラギノになっているので,異なる形式である筑紫を異質に感じた,ということである。
何かを書くとき,書き手はただ思ったこと,感じたことを書いているだけではなくて,書いた文字や文章をまた自らの思考に再取り入れしている。内的には同時に存在している様々な考えや感情を,文章というリニア構造で出力するわけだけれど,今度はそれが自分の内的な経験にフィットしているかどうかを,再検討するために入力の過程がやってくる。そんなふうに,書き手と,書き手によって出力された文章とは,対話的関係を持っている。それがかならずそうなのかはわからない。少なくとも僕はそういうふうに,文章と関係しているつもりである(そのくせ誤字脱字は多いし,意味が通らない文章になりがちである)。これはつまり,文章は自分が出力したものでありながら,出力されたあとは,独自の存在性を持っているということである。文章は僕自身であるけれど,でもまったく僕自身でもない。それは以前のコラム『意味の船,その船出』で書いたことである。だからこそ,自分で言ったことに自分でも驚く,といったことも起こるのである。
とにかくも,ここに,フォント形式の違いによって生じる異質さ,自分のものとして感じられない感覚の背景がある。筑紫を僕の思考の形式として使用する準備が,まだ僕のほうにできていなかったのである。これは単なる慣れの問題ではなく,自らの思考形式の素材として筑紫と関係することができなかったという問題である。
これはちょうど,心理療法という,これまで経験したことのない,特殊な対話の形式を持つ方法に取り組みはじめたときの感覚に似ている。悩み,困り,落ち込み,打ちひしがれ,混乱し,怒り,憎み,恐れ,妬み,羨み,考え,葛藤し,行き詰まり,打開し,愛し,そしてまた悩む。そのようにして自分なりに生きてきたところで,心理療法という場を設えた治療者のいるところで,奇妙で,異質で,しかしどうしても大事で,意味があると感じられるような作業を,治療者と被治療者の双方とも経験することになる。
この新しい形式に出会うときの経験は,自分自身の形式とは異なる要素を持つがゆえに,奇妙にも異質にも感じられる。それが,ヒラギノから筑紫に乗り換えてみたときの異質さの正体であるのではないかと思う。しかしだからといって,筑紫を使うことを止める気にはならない。それは,この新たな形式に魅力も感じるからである。自分とは異なる形式に触れることは,じつのところ,自分自身の形式に影響を及ぼす。そして僕たちは,自分の形式に影響を与える別の形式,それはすなわち自分とは異なる他者の形式を,求めずにはいられない(Bollasはこれを変形性対象と呼んでいる)。
自分が自分になるために,他者の形式が求められる。
自分が思考するために,他者の思考が不可欠である。
たとえそれが,最初は異質に感じられるかもしれないとしても。
いずれそれが,新たな形式として自分たちを育むかもしれない。
こうして,新しいフォントによって経験した違和感の正体に,少し形をもたせることができた。こうした理解はひとつの内容である。いまはこの内容がしっくりくるけれど,そのうち別の内容がもっとしっくりくる日が来るかもしれない。
そのとき,それを考える形式は,ヒラギノだろうか,筑紫だろうか,それ以外のフォントだろうか。
それとも,写真だろうか,音楽だろうか,絵だろうか,講義だろうか,踊りだろうか,夢だろうか。
あるいは,僕ではない誰かの形式によって,もたらされるかもしれない。
それでも,誰かの形式があるだけでは何も生まれない。必要なのは,自分と,誰かの,二つの形式である。
いつしか,その考えの出発点と区分けは,その明確性を失っていく。
なぜなら,このコラムの形式は筑紫だが,そこにはすでにヒラギノの形式が前提にあるのである。
ちょうど,心理療法という新たな形式の前から,人生で様々な形式と出会っていることと同じである。
僕と筑紫とヒラギノと。
あなたと僕となにかとで。
そのうち,何かが起こるでしょう。
(文責:淺田慎太郎)